【偽娘竹取物語】(1)

(C)Eriko Kawaguchi 2016-04-08
今は昔、竹取の翁(おきな)という者があった。野山に入って竹を取っては、様々なことに使っていた。名を讃岐造(さぬきのみやつこ)と言った。造は長年、顔は大したことないものの気立ての優しい耶穂という女と連れ添っていた。ふたりの仲はとても良かったものの、どうしても子供が授からない。
子宝恵綬に御利益があるという月読神社に二十三夜参りなどもしたものの子は得られなかった。
翁がもう子供はできなかったなあと諦めていた、52-53歳の頃(*1)、いつものように野山に入って竹を取ろうとした時、よく通っている所で、竹の中に根元の所が光っている竹を見る。何だろうと思って近づいて見ると、竹の筒の中が光っている。そこには上等な赤い衣に包まれた10cmほどの大きさの美しい容姿の赤ちゃんが居た。
「ここは私がいつも朝夕見ている場所だ。こんな所に居たというのはきっと私の子供になるべき人なのだろう」
と翁は言うと、てのひらに乗せて家に連れ帰った。そして妻の耶穂に預けて育てさせた。
翁と媼は「もう子供は得られないと思っていたのに子を授けて下さったのは、やはりずっとお参りしていた月読神社の御利益(ごりやく)なのだろう」と言い、月ごとにお参りを欠かさなかった。
この子は竹の中から見つけたので「竹子」という名を付けて育てたが、本当に美しい子であった。子供はすくすくと育った。
竹子は優しい性格で、その優しさを周囲に及ぼす力を持っていた。近所の子供たちが争いごとをしていても、竹子が近寄って「喧嘩はやめようよ」と言うとなぜか争う気持ちが減り、仲直りするのであった。
またこの子はいつも笑顔でいることが多く、この子が部屋の中にいるだけで、その部屋全体が明るく感じられるという不思議な子であった。
この子を見つけた後、竹取の翁が竹を取っていると、しばしば竹の中に黄金が入っている竹を見つけることが重なった。そこで翁はどんどんお金持ちになっていった。家も立派な物に建て替え、使用人も数人使うほどになった。
竹子が9歳の時のことである。
それは雨上がりの日であった。その日も翁と媼に連れられて月読神社にお参りに行っていたのだが、竹子は神社の参道の近く、崖のそばに見たこともないような白い美しい花が咲いているのを見た。
竹子は優しい性格なので花を安易に手折(たお)ったりしないのだが、近くで見てみようと思いそのそばまで寄る。
母の耶穂が「危ないよ」と声を掛けたのだが、その前に竹子は足をすべらせ、崖から落ちそうになった。
耶穂が悲鳴をあげる。竹子は崖の近くにあった木の根をつかみ、かろうじて落下はしなかったものの、自力であがることはできず、木の根を掴む手の力が尽きたらいつ落ちてもおかしくない状態である。
そこに12-13歳くらいの身なりの良い少年が走り寄った。竹子が右手で木の根をつかんでいたので、空いている左手を自分の両手でしっかりとつかむ。
そして
「誰か手伝え」
と大きな声で言った。
すると少年の従者らしい屈強な男性が2人そばに寄り、竹子の両手を1本ずつつかんで、「それ!」と掛け声を掛けて引っぱり、竹子を上に引き上げた。
「どちら様でしょうか。娘を助けてくださってありがとうございます」
と翁と媼は地面に頭を付けて少年と従者に感謝した。
「いや、名乗るほどの者ではない。しかし娘、美しいな」
「ありがとうございます」
「お互いもう少しおとなであったら、すぐにも求婚したい所だ」
などと少年は笑顔で言って、従者たちとともに去って行った。
助けてもらった竹子はその少年の後ろ姿をぼーっとした様子で見送った。
竹子はやがて15歳(*2)になるので、成人式をさせることにする。
昔は女は数え年の十五歳、今で言うと中学2年生で笄年(けいねん)である。
髪上げをして髪に笄(こうがい)を付け、女子の礼服である裳(も)を着せて、3日連続の宴を催したが、本人は帳(とばり)の内側に入れて、安易に人に顔は見せないようにする。しかしその声の美しさや、姫が吹く竹の横笛の音色の素敵さが、集まってくれた多数の人々に本人の美しさも連想させた。
成人名については三室戸斎部の秋田という人を呼んで付けさせた。秋田は「若竹(なよたけ)の赫夜(かぐや)姫(*3)」と名付けた。若竹とはまだ硬化していない柔らかい竹のこと、赫(カク/あかあか)とは明るく火が燃えている様で、この子がいることで夜も明るくなることを表している。
美しい姫がいるらしいと聞き、竹取の翁の家の周囲には、尊きも卑しきも多数の男が出没するようになる。彼らは一目姫の顔を見よう、一声姫の声を聞こうと待ち構えているものの、なかなか姫の顔を見ることはできない。文を贈る者もあるが、かぐや姫は一切お返事を書かない。
壁に穴を開けて覗き見しようとする者、木に登って覗こうとする者もある。
夜中に、あるいは壁を乗り越えて、あるいは地面に穴を掘ってまで侵入しようとする者まで出る始末で、翁は姫の部屋の外に武術の心得のある女房を置いて警戒せざるを得なくなる。
使用人に言伝を頼もうとする者もいるが、使用人たちは一切お断りするように言われているので、どうにもならない。
しかし難攻不落な女ほど男は燃えるものである。姫が自分を好きになるようにと祈祷したり、高価な贈り物をしようとする者もあるが、祈祷しても状況は変わらず、贈り物の類いも一切姫は受け取らなかった。
「竹や、今日もこれだけ文を頂いたのだけど」
と母の耶穂は言って、20通くらいの文が入った籠をかぐやの前に出した。
「だって私、男の人と結婚できないもん」
とかぐやは困ったように言った。
「そうだよね〜。どうしたものかねぇ」
と耶穂も困ったように言った。
「私が本当の女の子だったら良かったのにね」
「いや、お前は充分女の子だよ。でも男の子として育てられたかった?」
「ううん。私は男の子として育てられいても、いつか自分で女の子として生きる道を選んだと思う」
竹子は拾われた時、とても美しく華やかな衣に包まれていたので、翁はてっきり女の子と思い込んでしまった。しかし世話をするように言われた耶穂はその子におむつを付けようとして戸惑った。その子には女の子には余計な物が付いていたのである。しかし翁が「美人に育つかなあ」などと言っているので、耶穂はとても竹子の性別のことを言えず、女の子のように育てた。
そして実際に竹子は性格的に女の子であった。それは成長するにつれ明確になっていった。耶穂が何度か竹子の前に男の服と女の服を並べ、着たい方を着せてあげると言ったが、いつも竹子は女の服を選んだ。そして竹子は女らしい遊びを好んだ。まだ自由に外に出していた5〜6歳の頃、竹子はいつも近所の女の子たちと一緒に遊んでいた。
竹子が10歳になった時、耶穂はあらためて訊いた。
「お前は女になりたいのか?それとも男に戻りたいと思うか?」
竹子は答えた。
「私は女になりたいです。男にはなりたくありません」
「お前、女になるのであれば、やがてはどなたかの妻にならなければなりませんよ」
と耶穂に言われた時、竹子は1年ほど前、月読神社にお参りしていた時に崖から落ちそうになったのを助けてくれた男の子のことがふと思い出された。
「私、誰かの奥さんにしてもらえたらいいなあ」
「そうだね。この広い世の中にはお前のようなものでも良いと言ってくださる殿方もあるかも知れない」
耶穂は、女の子になりたがっている竹子が男っぽく育って行かないようにするため、竹子の「男の素」を取ることにした。それで帰化人でその手の作業の経験がある医者を密かに呼び、充分な報酬を提示して決して誰にも言わぬことと言って竹子の服の裙をめくり、股間を露出させる。
「これは・・・・」
とさすがに医者が驚く。
「両方の玉を取ってください」
と耶穂は依頼する。
「姫様、それでよいのですか?」
と医師は本人にも確認する。
「はい、お願いします」
と竹子は答える。
それで医者はその部分をよくよく水で洗った上で、更に酒を吹きかけると、竹子の玉袋を小刀で小さく切開し、中から玉を1個ずつ絞り出すようにして取り出しては、2個とも身体から切り離した。この間竹子は激痛に耐えていた。医師は切開した跡に新しい麻布(*4)を当て、傷が治るまで時々新しい麻布に交換するよう告げて立ち去った。
傷が治るのに一週間ほど掛かったし、その間痛みが続いていたものの、この年齢で玉を抜いたことにより、竹子は男のようなごつごつした筋肉質の身体になるのを避けられ、ヒゲやスネ毛が生えたりもせず、柔らかく脂肪質の身体で、声も普通の女のように高い声のまま今に至るのである。
かぐや姫には多数の求婚者が現れては消えたが、やがて5人の求婚者が残り、日々熱心に文をくれた。
耶穂はかぐやが本当に困っているようなので、伯母で巫女をしている都女に相談した。すると都女は占いを立てた上で
「その5人の求婚者にこういうものを要求しなさい。それを持って来たら結婚すると言うのです」
「でも、竹子はさっきも言ったように、実は女ではないのですが・・・」
「これを本当に持って来たら、その道具を使って、竹子を真の女に変えることができるのです」
「そうなのですか!?」
「やり方はそれぞれ詳しく書いたものを追ってまとめて渡しますから」
それで耶穂は都女が書いた5つの品の一覧を夫に渡し、5人の求婚者に提示してもらった。
「姫が申すには、あなた方5人の方々がみな素晴らしい方ばかりで、どなたに嫁いでよいか判断がつかないと申します。それで、今から申す物を最初に持ってきてくださった方に嫁ぎたいと申しております。どれも入手するのがひじょうに大変だと思うのですが」
と翁は言う。
「姫のことは何物にも代えがたいほど好きです。多少の困難があっても必ずやそれを手に入れてきましょう」
と5人を代表して、大伴御行(おおとものみゆき)が言った。
「それでは、石作皇子(いしつくりのみこ)様には、お釈迦様が母君から頂いて使っていたという仏の御石の鉢を。庫持皇子(くらもちのみこ)様には、東の海に蓬莱という山があり、そこに白銀を根とし黄金を茎とし白い珠を実として立つ木があるので、その一枝を折って持って来てください。最後の(*5)阿倍右大臣様には、中国の奥地にあるという火鼠の皮衣をお願いします。大伴大納言様には龍が首につけているという五色に光る珠を。石上中納言様には、燕が持っているという子安貝をひとつ取って持って来て下さい」
と翁は読み上げる。
この姫の依頼品を聞いた5人の貴人たちは内容に絶句し、
「要するに2度とうちに来るなという意味か?」
などと言いながら腕を組んだり、首をひねったりしながら帰って行った。
石作皇子は最初はもう諦めた!と思ったものの、しばらくする内にやはり何とかしたいという気持ちが起きる。そこでまずは「石作皇子は仏の御石の鉢を探しに天竺に出発なさった」という報せをかぐや姫の所に届けさせた。
そして皇子はその後自分が家に居ないように装うため、最初は隠れていようかと思ったものの、それでは食事などがままならない。そこで女装して、皇子に仕える女房の振りをしてしばらく過ごすことにした。
女性用の内衣・上衣を着て下半身には裙(くん:裳の一種)を穿く。髪も双髻に結わせ、ヒゲを良く剃った上でおしろいを塗り、口紅・頬紅を入れ、唇の両端には靨鈿(めんでん)を打ち、額には花模様の花鈿(かでん)も入れた。
石作皇子がそんな格好をしているのを見た父親の麻呂皇子は仰天する。
「お前、何やってるのだ?どこぞのなかなか靡かない姫の所に盛んに文をやっているとは聞いたが、もしや振られてもう男を辞める気になったか?」
「父上、私はしばらく旅に出ているということにしておいてください」
「それは構わんが、お前、女になりたいのか?」
「男が女になれるものですか?」
「普通そんなことは神様か仏様にしかできないが、唐土からの帰化人に一度聞いたことがある。遠い天竺の毘尼精舎という所に伝わる、お釈迦様の生母・摩耶夫人が使っていた鉢で、曼虎故羅という植物をすり下ろし、その汁を飲むと男が女に、女が男に変わるのだそうだ。お前、女になりたいのなら、天竺まで行って、その鉢を取ってくるか?」
「いや、実は姫からその鉢を所望されて、私は今その鉢を取りに天竺まで出かけたことになっているのです」
「なぜそなたが懸想している姫は、そんなとんでもないものを所望するのだ?」
「要するにまだ結婚したくないということなのでしょうが、私は何とか口説き落とすつもりです」
「まあ良いが、そんな格好していて、お前が誰かから文をもらうようになったりしても知らんぞ」
と父親は呆れたように言った。
そして父親の心配は当たってしまうのである!
麻呂皇子の家に、誰も知らない姫がいるらしいというのが、どこからともなく噂となってしまう。すると、その姫を一目見ようとする男たちが大量に発生する。
「しかし麻呂皇子の家に年頃の姫がいるなどという話は聞いたことなかったぞ」
「おそらくは、身分違いの女に生ませていたのを引き取ったのでは」
「確かに麻呂皇子様には、お子様は男の子1人しかおられないから」
「そのたったひとりの男の子であった石作皇子さまは何でも天竺までの旅に出られたとか」
「そんな旅、生きて戻って来られるかどうかも分からないよなあ」
「それで女の子でもいいから手元に置いておきたくなられたのでは?」
一度は力づくで何とかしようとする男が屋敷に侵入し、女装のまま寝ていた石作皇子が采女に起こされて慌てて床下に隠れて、何とか貞操(?)を守るなどという事件まで起きた。
文も日々大量に来るものの、むろんそんなものに返事など書けない。
「何だかかぐや姫の気持ちが分かったような気がしてきたぞ」
などと女装の皇子はつぶやいた。
その文を寄こす男の中には、かぐや姫の求婚者のひとりでもある大納言・大伴御行(おおとものみゆき)まで居て、皇子は呆れてしまった。
そして女装生活も3年をすぎた新月の晩、皇子は腹心の馬係の男1人だけを伴い夜に紛れて屋敷を出る。そして以前から目を付けていた大和国十市郡の古寺に行った。そして寺の賓頭盧(びんづる)像の前に置かれている古い鉢を暗闇に紛れてこっそり盗ると、持ち帰った。
皇子は自宅に戻ると3年間続けた女装を解き、男の姿に戻って化粧も落とし、鉢を錦の袋に入れ、造花の枝なども添え、それを持ってかぐや姫の家に赴いた。
かぐや姫は石作皇子が仏の御石の鉢を持って来たと聞き驚く。
「でも本物だったら、あなたそれで女の身体に変われるのでしょう?」
と母の耶穂が言う。
「ええ。伝説では曼虎故羅をその鉢で擦り卸すということになっているのですが、都女様が見た古文書によると実は二股の大根(だいこん)でもいいらしいのよね〜」
とかぐやは言った。
女の身体になれたら、別に石作皇子と結婚してもいいしと、この時かぐや姫は考えた。わざわざ遙か遠くの天竺までこんなとんでもないものを取ってくるほど熱心な人なら自分を大事にしてくれるだろうしとも考える。
それで翁を通して受け取った鉢を見ると歌も添えられている。
《海山の道に心を尽くし果てな石の鉢の涙流れき》
「本物であればおのずから光を発していると都女様はおっしゃってました」
と耶穂。
「ちょっと洗ってみましょう」
それでかぐや姫に仕えている女房に命じて鉢をきれいに洗わせる。それで見てみるものの、どこにも光るようなものは無い。
「これ偽物なのでは?」
それでかぐや姫は初めて石作皇子に返歌を書いて鉢に入れて返した。
《置く露の光をだにぞ宿さまし小倉山にて何求めけむ》
それを見た石作皇子は「ばれてる〜!」と思ってため息をつく。それで鉢はもうどうでもいいので、門の所に放り投げた上で、かぐや姫に再度歌を渡す。
《白山にあへば光の失するかと鉢を捨てても頼まるるかな》
しかしこの歌にはかぐや姫は返歌もしなかった。翁から「申し訳ありません。
姫が返歌もしないと言っております」と聞いた皇子はトボトボと帰途に就いたが、内心は
『でもかぐや姫からの返歌をもらったぞ。これ一生宝物にしよう』
などと少し得意な気分にもなっていた。
それで自宅に戻ると父親が
「お前、なんで男みたいな格好をしているのだ?」
と訊く。
「私は男ですから男の格好をしていますが」
「お前、女になったんじゃなかったの?」
「女になれるわけないじゃないですか!?」
「いや、俺はお前が女として生きていくつもりなのかと思ったから、男の身体でも構わんと言ってきた、清原の中将殿に、代理で返歌を書かせておいたぞ」
「え〜〜〜〜!?」
「今度の満月の晩に婚礼をするから、早く女の服に戻りなさい」
「ちょっと待ってください!私は男と結婚したくありません!」
「何を言っているのだ。この世には男と女がある。女は男と結婚するものなのだよ。私はお前を自分の跡取りにと思っていたが、お前が女として生きるのであれば仕方ない。女であるなら良き夫に仕えるのがよいのだ。清原中将は本当に凄い男だぞ。あれはその内きっと右大臣か左大臣まで出世する。それを支えてやれ。女の子を産んでその子が帝と結婚すればお前はやがては帝の祖母、私は曾祖父になれる」
「でも私は子供など産めませんけど」
「構わん。誰か適当な者に産ませて、お前が産んだ子ということにすればいいのだ」
「そんなぁ」
「今後は私もお前のことは皇子(みこ)ではなく皇女(ひめみこ)と思うことにしたから。それで中将の妻になる前に、せめてお前があまり男っぽくならないように、睾丸を取ることにするから」
「ちょっと待ってください。睾丸を取るなんて嫌です!」
「少し痛いと思うが我慢しろ。お前があまりに男らしくなってしまったら、さすがの中将も嫌がるだろうから。今日の午後にも、馬の睾丸を取るのに慣れている者を来させるように手配している」
「私って馬と一緒ですか?」
「良い妻になるのだぞ。これ、采女、石作皇女にきれいな服を着せて化粧もしてやれ」
「はい」
と言って采女(うねめ)が4人寄ってくる。
「ささ、皇女(ひめみこ)さま、向こうできれいなお召し物を着ましょうね」
「やめて! 助けて〜〜!」
と言うものの、皇子(皇女?)は采女たちに4人掛かりで連れて行かれてしまった。
3年前に時間を巻き戻す。
2番目の求婚者・庫持(くらもち)の皇子は、蓬莱山の金銀珠の木を持ってきてくれと言われた。皇子はそんなもの作ればいいではないかと考えた。
そこで表向きには「筑紫の国に行き、武雄温泉(*6)で湯治をして参ります」と言い、かぐや姫の家には「玉の枝を取りに蓬莱山まで行ってきます」と告げさせ、難波から本当に船に乗って旅立った。多くの人が皇子が旅立つのを見送る。
ところが実際には皇子は3日後、ごく少数の供を連れて小舟で畿内に戻って来る。
夜中に暗闇に乗じて上陸すると、山の中に小さな家を作り、三重の柵で囲って人が近寄れないようにし、その家の中にかまどを作って、鍛冶職人6人と一緒に籠もった。ここで、かぐや姫が言ったような「銀の根・金の茎に白い玉が実としてなる枝」を作らせようという魂胆なのである。
皇子と職人たちの作業は千日に及ぶ。
やがてかぐや姫が言ったような美しい枝ができあがった。
できあがった時、職人たちは長期間にわたる作業の疲れでみんな寝てしまったが、皇子はひとり、その枝を持って密かに難波に行った。そして自宅に「帰ってきたぞ」と使いをやらせる。そして自分は旅の疲れで倒れて苦しんでいる振りをする。そこに屋敷から召し使いたちがやってきて皇子を助け、玉の枝は長櫃に納め持ち帰る。するとこのことが多くの人に知れ渡り
「庫持皇子は優曇華(うどんげ)の花を持って帰ってきた」
という噂が立つ。それを耳にしたかぐや姫は少し焦った。
「私、どうすればいいのかしら?」
と母の耶穂に相談する。
「蓬莱の珠の枝は、それを掲げて女渦娘娘を祭る女化神社に3ヶ月と3日籠もり、その間に女化宣文を3333回書くと女にしてもらえるはずです」
と都女からもらった文書を読んで確認する。
「では庫持皇子には3ヶ月と3日待ってもらわないといけないですね」
とかぐや姫はため息をついてこたえた。
やがて庫持皇子のかぐや姫の家にやってくる。翁に玉の枝を渡すので、翁がそれを持って姫の所にやってくる。枝に歌が付けてある。
《いたづらに身はなしつとも玉の枝を手折らでただに帰らざらまし》
その玉の枝を見ても、姫がすぐには表に出て行って皇子と会おうとしないので翁は姫を諭す。
「お前が無理な難題を言ったのに、皇子は男らしく旅に出て、きっと物凄い苦労をしてこの枝を手に入れ持ち帰ったのだぞ。なぜお前は皇子の苦労に報いようとしないのだ?」
かぐや姫としてはそんなに熱心な皇子であれば結婚するのはやぶさかではないものの、今すぐ結婚するのは不可能な事情がある。それであれこれ言い訳を言う。それで翁は「お前から説得してくれ」と妻に言うと、自分は婚礼のための寝所の準備を始めた。
かぐや姫が、さてどうやって3ヶ月もの間皇子を待たせておくか、その言い訳を考えようと悩んでいる間に、翁の方は皇子にお酒など出してもてなし、皇子ももうかぐや姫を手に入れた気になって、機嫌良く、この玉の枝を得るまでの長い長い冒険談を話し始める。
嵐に吹かれ、船が沈みそうになり、食料が尽きて草の根や貝を取って命をつなぎました。ある時は怪獣に襲われ必死で逃げましたし、ある時は船を寄せた島が女護島で島の者が皆女なのです。「ここは女だけの島である。男は来訪者であっても全て女になってもらわなければならない」と言われて女に変えられそうになり、慌てて逃げ出しました。命は捨てる覚悟の旅ですが、女の身に変えられてしまってはかぐや姫と結婚できませんから。
そのような散々な苦労の果てに五百日目に海の中に微かな島の影を見ました。
寄せてみると大きな山があります。船を着けて見て回っていたら《うかんるり》(*7)と名乗る天女が現れ、その天女の後を追うように山の中に入ると、金色や銀色や瑠璃色の川が流れ、宝石の橋が架かっていました。その山に多数の素晴らしい木々が生えていたのです。この枝よりもっと凄いものもありましたが、かぐや姫がおっしゃったのと違うものではいけないと思い、この枝を折って持ち帰りました。帰りは追い風となり四百余日で帰ってくることができました。
そんな話を皇子はし、翁は皇子の苦労をねぎらって、酒を酌み交わし、意気投合して話に花が咲いていた。
皇子が大きな声で話をしているので、別室にいるかぐや姫にも聞こえてくる。
「女護島にいけば女に変えてくれるって素敵。私そこに行きたい」
などとかぐや姫は言う。
「でも皇子様がその時に女になってしまわれていたら、私普通に皇子様と結婚できたかもね」
と付け加えると耶穂は吹き出した。
「庫持皇子様は身体ががっしりしていますから、実際に女になったとしても女に見えないかも知れませんね」
と耶穂は言う。
「そういえば石作皇子様は女になってしまわれたらしいですよ」
「え〜〜〜!?」
「竹子に振られたことで傷心して、もう男としては生きていけないとお思いになったのかも知れませんね」
「気の毒なことしたなあ。でもどうやって女になられたのです?」
「睾丸を取っただけのようですけどね」
「なるほどー」
「あなたと同じね。でも石作皇子様は細くて華奢なお身体だから、女の服を着れば女でも通りますよ」
「そうかも知れないなあ。でも女になってしまわれても、それで幸せになってくれたらいいけど」
「清原中将の妻になられたようです」
「へー!」
「男の身体でも構わないから結婚してくれと言われたとか」
「やはり、そういう人居るのね!」
「ええ。竹子もそういう人が現れるといいね」
「はい」
そんな雑談をしながらも、かぐや姫と耶穂は一緒にあれこれ思案した末、皇子の家の繁栄を祈って神の山に籠もって祈祷をしてから嫁ぎたいとでも言うしかないという結論に達する。それで耶穂も付き添って、それを伝えに行こうとした時、家の玄関の方がなにやら騒がしいのに気づいた。
何事かと家の者に問わせると代表格の漢部内麻呂なる者が述べる。
「私たちは庫持皇子と共に千日に亘って山の中に籠もり、立派な金銀宝石の枝の細工を作りました。皇子は完成のあかつきには褒美も取らせるし官職も約束しようとおっしゃいました。しかしまだ私たちは報酬を頂いておりません。
皇子を探していたのですが、皇子はこちらの姫様とご婚礼なさるとのことを聞きました。それではあの金銀宝石細工も姫様への贈り物であったのだろうと思い、こちらの家に参りました。どうか私の弟子共に褒美を下さいますよう、皇子様にお伝えください」
それを聞いたかぐや姫は笑い転げた。
「本物の蓬莱の木の枝かと思ったのに。そんな呆れた嘘であったとは」
と言って、返歌をしたためる。
《まことかと聞きて見つれば言の葉を飾れる玉の枝にぞありける》
その歌を付けて玉の枝を皇子に返させた。それをうけとった皇子はバツが悪すぎて、その場にもいたたまれず、といって人が大勢注目している中で帰るのも恥ずかしく、少しほとぼりが冷めた夕刻になってあたりが暗くなってからこそこそと退出した。
なお、かぐや姫は職人たちに「ご苦労様でした」と言って褒美をやったので職人達は喜んで帰ったものの、皇子はその職人たちに八つ当たりして彼らが立てなくなるほどまで打ちすえた。
そして皇子は何という大恥を掻いてしまったものかと自分の行動に恥じ入り、そのまま誰にも告げずひとりで山の中に入ってしまった。
家人が探したものの、誰も皇子を見つけることはできなかった。
また3年前に戻る。
3番目の求婚者、右大臣・阿倍御主人(あべのみうし)には「唐土にある火鼠の皮衣」が所望された。
そこで右大臣は唐にいる知人の王慶という人に手紙を書き、配下の小野房守という人に託して唐土に行く船に乗せた。阿部右大臣からの手紙を受け取った王慶は、「火鼠の皮衣などというものは唐の国にも無いと思う。しかしもしかしたら天竺あたりで入手したものが、長者の家などにあるかも知れないから探させよう」
それで王慶が探してくれた所、昔天竺から来た僧が持っていたというものが西の山寺にあるということが分かり交渉して買い取ることにした。しかし代金が阿部右大臣が持たせたものでは足りなかったので、王慶自身がお金を足してやっと買い取ることができた。
やがて小野房守が帰国する。
「王慶殿に代金の不足分を建て替えてもらいましたので、使いの者にあと五十両渡して頂けますか?」
「もちろんだ」
と言って右大臣は五十両を渡し、西の方の王慶のいる方角に深々と伏し拝んだ。
そして右大臣はこの火鼠の皮衣を持ってかぐや姫の所に行く。見るとそれはとても美しい毛皮であった。右大臣は歌も添えている。
《限りなき思ひに焼けぬ皮衣袂乾きて今日こそは着め》
しかしかぐや姫もここまでさんざん偽物に付き合わされていたので
「本物の火鼠の皮衣でしたら、火を点けても燃えないはずですよね。ちょっと火を点けてみてもいいですか?」
と尋ねさせる。
右大臣も同意し、皮衣に火をつけてみた。
するとその皮はめらめらと燃えてしまった。
「偽物であったか」
と右大臣もそれを見てがっかりして言う。
それでかぐや姫は《名残りなく燃ゆと知りせば皮衣、思ひのほかに置きて見ましを》
と返歌し、右大臣はその歌を持って帰って行った。
さてまた少し時を戻す。
4人目の求婚者、大納言・大伴御行(おおとものみゆき)に課されたものは「龍の首についた五色の珠」である。
大納言はかぐや姫の課題を聞いて帰宅すると、配下の者を一堂に集めて言った。
「龍の首についた五色の珠を取ってきた者には何でも願いの物をやるぞ」
しかし配下の者たちは困惑する。
「そんなものどうやって取って来いとおっしゃるのですか?」
大納言は言う。
「男が女になれ、女が男になれと言うのでもない。唐土や天竺まで行って来いというのでもない。龍はこの国にもいて、しばしば天に昇ったり降りてきたりしているはずだ。それを捕まえればよい。貴人の家来というものは、主人の命令があれば、命を捨ててでも従うべきものである」
それで家来の中でも主だった人が言った。
「分かりました。困難な物でもご命令とあらば、探しに行って参ります」
それで大納言は出かける者たちに旅の衣服、食料品、旅費、など必要な物を何でも持たせて出発させた。そして自分は
「私は彼らが戻って来るまで精進潔斎していよう」
と言って、部屋の中に籠もっていた。
家来たちが探索に出ている間に、大納言はかぐや姫のために豪華な建物を建て漆を塗り蒔絵で飾った壁を作る。綾織物に絵を描いたものを内装をしていく。
またかぐや姫と結婚するのだからと言って、現在の奥さんを離縁してしまう。
そうして待っていたものの、年を越しても出かけて行った家来たちからは何も音沙汰が無い。とうとう大納言は自ら探索に出かけることにする。従者を2人だけ連れて難波の港に行き、私の強弓で龍など射(い)殺して珠を取って来よう、などと威勢のいいことをおっしゃって船を出す。そして、あちこちの海を航海してまわり、船はやがて九州の付近までやってきた。
にわかにあたり一面が暗くなり激しい風が吹く。船は木の葉のように舞って方角も分からなくなり、雷も激しく、もう船が沈むのではないかという感じである。大納言は船頭に
「これはどうしたことか?」
と訊く。
「私も長年船に乗っておりますが、こんな物凄い嵐に遭ったのは初めてです。
これはきっと龍の珠を取ってやるなどと言っていたので龍神様が怒っているのです。龍神様に謝ってください」
それで大納言は船の上では船頭の言うことを聞くものだとおっしゃって天に向かって祈る。
「私は未熟者で龍を殺してやるなどと思っておりましたが、それは間違いでした。今後は龍の毛1本でさえ動かそうとは思わないことにします」
大納言がそう誓約の言葉を言うと、ほどなく雷雨はやみ、やがて強い風が吹いてきて船はその風に押されてどんどん進んだ。わずか3日で播磨の明石の浜に漂着した。
大納言は激しい嵐のせいで、とても立ち上がれないほどの様子であった。播磨の国の国司が助けてくれて、輿に乗せて何とか都の大納言宅に連れ返した。
まだ大納言が体力を回復できずに寝ているうちに、龍の珠を探しに派遣していた家来が1人戻って来た。
「私もさんざん探し回ったのですが、どうしても龍の珠は手に入りませんでした。しかし大納言様も手ぶらでご帰還なさったと聞き、お咎めは無いかも知れないと思い、帰参しました」
と言う。
「お前、よく龍を殺さなかった。龍は雷の仲間なのだ。万一龍を殺していたらたくさん雷が落ちて大勢の人が死んでいたろう。私に龍を殺させようとしたかぐや姫という奴は、きっと大盗人の極悪人に違いない。お前たちもあの屋敷には近寄るなよ」
と完全にかぐや姫のことは熱が冷めてしまったようである。
その様子を見て、龍の珠を探しに行っていた他の者たちも次々と帰還する。
大納言はその者たちにみな褒美を取らせた。
そして一部始終を聞いた、(離縁された)元の妻は腹の皮がよじれるほど大笑いしたということである。
また時を戻す。
5人目の求婚者、中納言石上麻呂に課されたものは「燕の子安貝」であった。
中納言は家に帰ると家来たちに
「燕が巣を作っていたら報せるように」
と言う。
「何をなさるのですか?」
と家来たちが訊く。
「燕の子安貝を取るのだ」
と中納言は言うが、家来たちは
「そのような物は見たことありません。燕を殺してみてもそんなものは出てきませんよ」
と言って、中納言の計画に否定的である。
しかしその内ひとりの者が言う。
「大炊寮の御飯を作っている所の屋根には穴ごとに多数の燕が巣を作ります。
あそこに高い足場を組んで監視していたら、たくさんの燕が卵を産む所を見られるのではないでしょうか」
そこで中納言は家来20人ほどを連れて大炊寮に行き、足場を組んで監視させた。
ところがそんな間近で見られていては燕たちは巣に近寄らない。どうしたものかと思っていた時、倉津麻呂という人が申し上げて言う。
「こんなに近くで見ていたら燕はとても近寄りません。足場は撤去して、紐をつけた大籠を用意し、その籠の中にひとりだけ入って、燕が卵を産もうとした瞬間に綱を引いて籠を引き上げ、さっと子安貝を取ればいいのです」
「しかし卵を産もうとするのはどうやったら分かるのだ?」
「燕は卵を産む前に、しっぽを揚げて7度回ってから産むと申します」
「よし、やってみよう」
それで中納言は足場を崩して片付けてしまい、綱をつけた籠を用意した。それで家来が入って、卵を産みそうな燕がいたら即引き上げて巣に手を突っ込むものの誰も子安貝を取ることができない。
「お前らやり方が下手なのだ」
とおっしゃって、とうとう自らその籠に乗る。
そして卵を産みそうな動作をした燕が居たので大急ぎで引き上げる。中納言が巣に手を突っ込むと何か硬いものに触れた。
「やった。掴んだぞ」
とおっしゃるので綱を戻して籠を降ろそうとしたのだが、途中で綱が切れてしまい中納言はかなりの距離を落下し、更に鼎の上に落ちてしまう。
「中納言様!」
と家来たちが駆け寄る。
「痛たたたた。しかしわしは子安貝を取ったぞ。灯りを持て」
とおっしゃるので紙燭に火をつけてみると、中納言が握っていたのは燕の糞であった。
中納言は今更ながら自分が随分子供じみた試みをしたものだと思い恥じらって、落ちた時に痛めた腰もかなり良くなかったことから、伏せってしまう。そして人が自分を笑うのではないかと思うと心労がかさむ。更に恥ずかしがって医者にも見せなかったため、容態はどんどん悪化していく。
中納言の容態がよくないようだと聞いたかぐや姫は、お見舞いの歌を届けた。
《年を経て浪立ち寄らぬ住之江の待つかい無しと聞くはまことか》
これに対して中納言は姫から文をもらったことを喜び、このような返歌を書いた。
《甲斐はかくありけるものをわび果てて死ぬる命をすくひやはせぬ》
そして歌を書いてすぐにそのまま亡くなってしまった。その話を聞いて、かぐや姫はさすがに気の毒なことをしたと思った。
かぐや姫という娘が、誰にもなびかず、無理難題を言われて身を滅ぼしてしまった者も出ているという話を聞き、帝(天皇)が
「男たちがそれほどまでに夢中になる娘、どの程度の美貌なのか見て参れ」
と中臣房子という者に命じた。
それで房子はかぐや姫の屋敷まで行き、帝の命令でかぐや姫がどの程度の美人なのか見てくるように申しつかりましたので会わせて下さいという。
ところがかぐや姫は「私は大した美人でもないので、とてもお目にかかれません」
と言う。
「そんなことを言ってはいけない。帝の使者をないがしろにはできないだろう?」
「帝など私のような者には恐れ多すぎて、とても顔など見せられません」
どうしてもかぐや姫が使者と会おうとしないので困った翁がそれを告げると
「私は会ってくるよう帝から命じられてここに来ております。会わずに帰れば私が罰せられます。帝の命令をどうしてこの国に住む者が拒否できましょう?」
と使者は半ば呆れて言う。するとかぐや姫は
「帝の命令に反するということでしたら、どうぞ私を殺して下さい」
と返事をした。
かなりのやりとりをしたものの、どうしてもかぐや姫が使者と会おうとしないので、根負けした房子はいったん宮中に戻ってそのことを帝に報告する。
「さすが魔性の女だな・・・・」
と帝も思い、忘れてしまおうと思ったものの、やはりどうにも気になる。そこで帝は翁を呼び出して言う。
「そちの娘のかぐや姫を参内させよ。朕が使者を遣わした(*8)のに会おうとしないとは何たる不届きな奴だ」
「あの娘は決して宮仕えなどしないと申しております。しかし陛下の仰せですので勅命をお伝え致します」
と翁は恐縮して言う。
「姫を朕にくれるなら、そなたに五位の位を授けるぞ」
「ありがたきお言葉です」
それで翁は自宅に戻るとかぐや姫を説得するのだが、姫としては自分が男と結婚できない身体なので、その命に従う訳にはいかない。
「私はそのような宮仕えなどできません。どうしてもとおっしゃるのであれば父上が五位の位をもらえるように、いったん宮中に向った上で、すぐに自殺致します」
と姫は言う。
「死んではならない。我が子を失うくらいなら位階など要らない。なぜお前はそのように頑固なのだ」
「私が適当なことを言っていると思ったら宮仕えをさせてみてください。そして私が死なずにいるかどうか見ていて下さい。私のために真摯な愛を持って下さり命まで落とした殿方もおられます。それなのに帝になら簡単に従うようでしたら、私のために亡くなった人たちに申し訳ないです」
「私は何よりもお前の命が大事だ。仕方ない。どうしても参内できないと帝に申し上げよう」
それで翁は宮中に行き、かぐや姫の気持ちを伝える。帝は参ったなと思ったものの、突然思いつく。
「そなたの家は山の麓にあったな。狩りに行ったついでということにして、そなたの家に入ってしまおうか」
「そうですね。あの子がぼんやりしている時に不意打ちをすればあるいは娘の姿を見ることができるかも知れません」
と翁も答える。
それで帝は日を置いて狩りをすると言ってごく少数の供を連れてお出かけになり、唐突に翁の家に「邪魔するぞ」と言って入ってくる。そして姫付きの女房たちが止めるのも聞かずにずかずかと姫の部屋まで入って行ってしまう。
かぐや姫は突然の闖入者に驚いて帝を見た。帝は「なるほど、こんなに美しい姫だったのか」と感動した。帝は姫を見ていて何か懐かしいような思いが込み上げてきた。この娘、どこかで会ったか?
かぐや姫は無言で帝の姿を見ていたが、ふとあることを思い出した。
「陛下、もし違ったら申し訳ありません。もう12年ほど昔、月読神社の参道で崖から落ちそうになった娘を助けたりはしませんでしたか?」
「あ!お前はあの時の娘か!」
と帝はおっしゃった。
かぐや姫が9歳の時に崖から落ちそうになったのを12-13歳くらいの少年が助けた。
それが実はお忍びで月読神社に参拝しようとしていた東宮、今の帝だったのである。
「かぐや姫。あの時私はおとなになったらそなたに求婚したいと言った。今でもその気持ちは変わらないぞ。今すぐ朕と一緒に宮中へ参ろう」
と帝は言う。
「申し訳ありません。あの時のことは感謝しておりますが、私は陛下と一緒に宮中に参る訳にはいきません」
それで帝はかぐや姫を捕まえようとするのだが、姫はするりと逃げてしまう。
ふたりはしばらく部屋の中で鬼ごっこのようなことをしたものの、どうしても帝はかぐや姫を捕まえることができなかった。
「そなたなんて足が速いのだ。とても女人の足とは思えん」
と帝はハアハア息を吐きながら言った。
「そうですね。私は女人ではなく男かも知れませんよ」
「それは戯れがすぎるぞ、姫。こんな美人の男がいる訳が無い。男だと言うのであれば朕に確かめさせろ」
「私を陛下おひとりで捕まえることができたら、男なのか女なのかを確かめてもよいですよ」
「よし。捕まえてやる。者共手伝うなよ」
と供の者に釘を刺してから、また鬼ごっこをするものの、どうしても姫が捕まえられない。
「分かった。今日の所はそなたを連れていくのを諦める」
と、とうとう帝は疲れ果てて言った。
《帰るさの行幸もの憂く思ほえて背きてとまるかぐや姫ゆゑ》
(私の意に背いて家に留まろうとするかぐや姫のせいで帰りの行幸が辛く思える)
と歌を詠むと、かぐや姫はその場でお返事をする
《葎はふ下にも年は経ぬる身の何かは玉の台をも見む》
(雑草の生い茂るような身分の低い家で育った私のようなものがどうして帝の所になど参ることができますでしょう)
しかしこの行幸を機会に、帝は度々かぐや姫に文を送るようになり、かぐや姫も帝の文にはきちんと毎回お返事を書いた。
誰にも手紙の返事など書かなかったかぐや姫が帝の恋文には返事をしているらしいという噂が立つ。
「帝を狙っていたから、大臣様の求婚も大納言様の求婚も断り続けたのか」
「いや、それが元々帝は小さい頃に、かぐや姫と会ったことがあったらしいぞ」
「そんなことがあったのか」
「なんでもお互いまだ幼かったのに、帝、当時はまだ東宮であらせられたのだけど、その場でかぐや姫に求婚なさっていたらしい」
「そうか。かぐや姫は既に帝に求婚されていたから、他の男の求婚を断り続けたのか」
「だったら、それは純情物語ではないか」
今まで冷たい女だ、男を滅ぼす酷い女だと言われていたかぐや姫の株が、この話でかなり上がった雰囲気もあった。
「でもだったらなぜかぐや姫はすぐに帝と結婚しないのだ?」
「お前、陛下と結婚しないの?」
と耶穂は姫に尋ねた。
「身体をどうにかしないと結婚できないよぉ」
とかぐや姫は困ったように言う。
「思い切ってえいやと切り落としてしまおうか?」
とかぐや姫は思い詰めたように言う。
「切り落とすだけでは、殿方と交われませんよ」
「だよねぇ。何とかして女の身体に変わる方法って無いのかなあ」
かぐや姫と帝が文を取り交わすようになって3年が過ぎた。
7月15日の満月の晩、かぐや姫はその月を見て涙を流していた。
「お前、一体どうしたの?」
と母の耶穂が心配して言う。
「いえ、何でも」
と最初はかぐや姫も言っていたものの、その後毎晩のように月が出るのを見ては涙を流しているので、とうとう翁が
「お前は月を見てはならない」
と禁止してしまう。
月を見ることを禁じられたかぐや姫が、その後、ずっと自分の部屋で物悲しい様子をしているので、母は心配して再度かぐや姫を問い糾す。すると姫は驚くべきことを言った。
「来月の満月の夜、月から使者が来ます」
「え? お前、月の物が来るのかい?」
と母は驚いて言う。元々男の身体であったかぐや姫に月経が来る訳がないと耶穂は思っていたのである。
かぐや姫は泣いていたのをつい苦笑してしまい母に告げる。
「いえ、月の物が来たらいいのですけど。そうではなくて、月から私を迎えに使者がやってくるのです」
「どういうこと?」
「先月の満月の夜、封印されていた記憶が蘇りました。私は元々月の住人だったのです。それが悪いことをして罰としてこちらの世界に転生しました。しかし罰の期間が終わってしまうので、私は月に戻らなければならないのです」
驚いた耶穂は夫に相談し、それで驚いた翁は帝にそのことを申し上げた。
「ここまでわが心を奪われたかぐや姫を、やすやすと月の者に渡す訳にはいかない」
とおっしゃって、2000人の兵を率いてかぐや姫の家に行き、警護に当たった。
そして8月15日の夜。
帝の兵が警戒する中、突然月がふだんの満月の十倍ほどの明るさに輝き、まるで昼間のように明るくなるとともに、その月の中から貴人がひとり降りてきた。
帝の兵たちは弓矢を射ようとするものの、ほとんどの者がその雰囲気に圧倒されて身動きできない。数人気丈な者が何とか弓を引いたものの、矢はあらぬ方向に飛んで行き、貴人には当たらない。
やがて貴人が地上まで降りてくると、近くに居た者は全て石のように固まってしまった。木の葉が落ちる途中で停止している。時というもの自体が止まってしまっているようである。
「さあ、迦具也彦、帰るぞ」
と貴人は言ったのだが、家の中から出てきたかぐや姫を見て戸惑うように言う。
「なぜそなたは、まるで女のような格好をしているのだ?」
「私はこの24年間、こちらの世界では女として暮らしておりました」
「何とまあ。お前は月の世界では乱暴な男で8人も人を殺した故、優しい心を持つことを誓わせて地の世界に落としたはずが」
「優しい心を持った結果、女の心になってしまったのかも」
「しかし、お前、男の印が付いていたのでは?」
「ええ。でもそのような物が付いていても、私の心はもう女なのです。ですからこの世界では女として生きてきました」
「そういえばお前、なぜヒゲが生えていない。なぜ女のような声をしてる?」
「私が女の心を持っていることを知ったこちらの世界での母が、医者に頼んで男の素(もと)の玉を取り除いてくれました。おかげで私は女のように育つことができました」
「徹底しているな」
「それとごめんなさい。私、こちらの世界では女ゆえに、男を随分惑わせて、死なせてしまいました」
「なぜそうなる?」
「だって私、女としては不完全で、男の方の妻にはなれない身体だから、どんなに熱心に求婚されても、それを受け入れられないのです」
「うむむむ」
「それで求婚をお断りしている内に、皆さん亡くなってしまって」
「お前それでは罪を償うどころか、罪が増えてしまっているではないか」
「自分が完全な女でないことが心苦しかったです」
「何人殺した?」
と貴人はかぐや姫に訊いた。
「あ、えっと・・・庫持皇子が山に入って多分自殺なさったようですし、石上中納言様は事故でお亡くなりになりました。大伴大納言様はかなり身体を痛められ治るのに2年ほど掛かりました。石作皇子様は、私に思いが届かなかったのを苦に男を辞めて女になってしまわれました。あと、私の部屋に忍び込もうとして木や屋根から落ちて亡くなった方が3人、穴を掘って侵入しようとして埋もれて亡くなった方が2人、ほかに恋い焦がれて衰弱して死んでしまった方が10人ほど」
「お前、大量殺人しているではないか?」
「済みません。私が完全な女だったら、早い内にどなたかの妻になることでそのような悲劇は防げたのですが」
貴人は腕を組んで悩んでいた。
「とりあえずお前の刑期は延長する」
「はい」
「17人殺して、1人大怪我して、1人男を辞めるはめになったのであれば、殺した者1人につき3年、怪我した者1年、女になってしまった者2年で合計54年、刑期を延長する。だからあと54年こちらの世界に居ろ」
「分かりました。ありがとうございます」
「しかしそなたが、今のような身体のままなら、更に死者が出そうだな」
「帝も危ないです」
「仕方ない。お前、完全な女になれ」
「はい!」
それで貴人は懐から赤い薬と青い薬を取り出した。
「赤い薬は附女(ふじょ)の薬、青い薬は附士(ふし)の薬だ。附女の薬を飲めばお前は本当の女になる。青い薬を飲めば完全な男に戻る」
「附女の薬、頂きます」
とかぐや姫は言うと、赤い薬を飲んだ。
すると姫の胸のあたりが膨らみ始め、ふつうの大人の女ほどの乳房ができた。
お股の所にあった男の印がどんどん小さくなり、やがて身体の中に吸い込まれ、そこが穴になってしまう。穴はどんどん広がって皮膚を引っ張るので、やがてお股の所には縦の割れ目ができてしまった。
かぐや姫は自分が完全な女の身体になったことを認識し、物凄く嬉しい気持ちになった。
「あら?どこか怪我したのかしら」
とかぐや姫はつぶやく。お股の所に血が流れている。
「それは月の物だよ。お前女になったからな」
「ちょっとお待ちを。処置しなければ」
と言ってかぐや姫はその部分に布を当て、服を汚したりしないようにした。
こんなことをするのは初めてだが、やり方は知らないと変に思われると言われて、母から習っていた。
「嬉しいです。月の物は大変そうだけど、これがあることは女の証です」
「では54年後に再度迎えに来る。それまでにお前、殺してしまった男たちの菩提でも弔うとよい」
「はい。あの父上」
「うん?」
「私のせいで女になってしまわれた石作皇女様ですが、いっそあの方も完全な女にしてあげられませんでしょうか?」
「では赤い薬をもうひとつやるから、お前が届ければ良い」
「はい!」
それでかぐや姫はもうひとつ赤い薬を受け取った。
「では帰る」
と言って、貴人はまた天に登って行った。月の明るさが元の程度に戻った時、竹取の翁たち、帝たち、兵たちが意識を取り戻した。空中で止まっていた木の葉も地面に落ちた。
「これはどうしたことじゃ? 月の使者はどこに行った?」
と帝が言うので、かぐや姫は
「帝の軍勢に恐れをなして帰って行ってしまいました」
と答える。
「おお、そうか!」
「陛下、私は本当は月に帰る所だったのに、陛下に邪魔されてしまいました。
責任を取って、私を陛下のおそばに置いてください」
「おお、それは責任を取ってやるから、朕の妻になれ」
「はい!」
完全な女の身体になり、もう男の求婚を断らなくてもよくなったかぐや姫は明るく元気に返事をした。
帝とかぐや姫のやりとりを聞いた竹取の翁と妻の耶穂もたいそう喜んだ。
「かぐや姫を育てて二十余年になります。やっと結婚してくれてほっとしました」
と翁は言った。
「父上、ほっとして逝ってしまわないでくださいね」
「お前の子供が成人するまでは頑張る」
と翁は言うが、媼はその件に関しては心配そうな顔をしていた。
「それで月の使者から妙薬を頂いたのですが」
と言って、かぐや姫は帝に青い丸薬を見せる。
「これは女が飲むと、身体が男に変わってしまう孵士(ふし)の薬というものだそうです。これを私、飲んでもいいですか?」
「とんでもない!そなたが男になってしまったら、朕は女にならなければ結婚できなくなるではないか」
「女になるのも良いですよ」
「良くない。その薬を貸せ。お前がこんな変な物を間違っても飲んだりしないよう、この薬は焼いてしまおう」
帝はそう言って、その薬を駿河の国にある高い山の頂上まで持って行き焼かせた。
附士の薬を焼いた煙はそれからかなり長い間、頂上からたなびいていたが、その煙にあたると、女が男に変わるらしいという噂が立ち、男になりたい女が何人もその山に登ったという。これが今の富士山である。
またかぐや姫は赤い薬の方を清原の中将に手紙を添えて送った。それを受け取った中将はひそかに石作皇女に飲ませた。
「え?私どうしちゃったの? きゃー!胸が膨らんでくる。あっ、おちんちんが短くなっていく!」
本人が驚いている間に身体はみるみる内に変化して、完全に女になってしまった。
「いやーん。私何だか女みたいな身体になっちゃった」
「だから私の真の妻になればいいのだよ」
と言って中将は石作皇女に口付けをし、抱きしめた。
一方のかぐや姫は帝と盛大な結婚式を挙げた。
たくさんの臣下から多数の贈り物が届けられた。かぐや姫はその中にあの庫持皇子からの贈り物と歌があるのに驚いた。
生きておられたのか! でも月の父君には黙ってよう。皇子様が生きていたら、私、刑期を3年減らされて51年後に月の世界に戻らなければならなくなってしまうもの、とかぐや姫は考えた。
帝の女御(*9)となったかぐや姫は、本来の周囲を明るくする性格を発揮した。
姫に付いた女官たちは、最初は「多数の男たちを死に至らしめた冷たい女」と聞いていたので緊張したものの、姫が優しく接してくれるので、すぐに打ち解け、かぐや姫が住まう殿舎(*10)はいつも朗らかな笑いで満ちるようになった。
また、かぐや姫は何かに付けて他の妃や女御たちを立てたし、贈り物も欠かさなかったので、最初は帝のお渡りが圧倒的に多いかぐや姫に嫉妬していた彼女たちも次第に姫に優しくするようになっていった。
1年後、かぐや姫は玉のような王子を産み落とした。帝は政治的な面倒を避けるためすぐに臣籍降下させたものの、たいそうな可愛がりようで、何度も出産のため宿下がりしている姫を訪ねてきた。
「お前、本当に子供を産んだね」
と耶穂は言った。
「私、月の神様に本当の女にしてもらったんだよ」
「そうだったのか。だったら、また月読神社にお参りに行かねば」
「うん、お願い。私が出歩くとお供や警護で大袈裟なことになっちゃうし」
「でも母上」
「なんだい?」
「女の身体って、すっごくいいね」
すると耶穂は「私は男になったことがないから分からないけど、まぐわいは気持ちいいよね」
と笑って言った。
「うん、凄く気持ちいい!女になって本当に良かったなあと思っているよ」
とかぐや姫は笑顔で答えた。
■5人の求婚者と交わした歌の解説
《海山の道に心を尽くし果てな石の鉢の涙流れき》
(海と山を越えて遙かな旅路は心が尽きるほど大変でしたが、石鉢を手に入れた時は血の涙が出ました:石の鉢・ちの涙と掛詞になっている)
《置く露の光をだにぞ宿さまし小倉山にて何求めけむ》
(本物であれば自ずと光るもののはずですが、露の光のようなものさえ宿していません。(ごく近くの)薄暗い小倉山で一体何を探してきたのですか?:「暗い」と「小倉」が掛けてある。また光を宿してないから暗い、というつながりにもなっている)
《白山にあへば光の失するかと鉢を捨てても頼まるるかな》
(白き尊き山のようなあなたに出会って恐れ多すぎたためきっと鉢の光は消えてしまったのでしょう。もう光を失った鉢は価値が無いので私は捨てましたが、私も恥を捨てて再度あなたに求婚したい:「鉢を捨てる」と「恥を捨てる」を掛けている)
《いたづらに身はなしつとも玉の枝を手折らでただに帰らざらまし》
(たとえ死んでしまったとしても、玉の枝を折らずに手ぶらで帰ってくることは考えられませんでした)
《まことかと聞きて見つれば言の葉を飾れる玉の枝にぞありける》
(本物かと思って見ておりましたのに、あなたの言葉を飾るだけの玉の枝だったのですね)
《限りなき思ひに焼けぬ皮衣袂乾きて今日こそは着め》
(限り無き私の思いで焼けてしまった皮衣、涙に濡れた袂も乾いて、今日こそは着ましょう:衣を着るというのが婚礼衣装を着るというのを連想させている。
思ひ(おも火)で焼けるという部分も掛詞/着めではなく見めになっているテキストもある。皮衣を見ると結婚の意味の見るの掛詞)
《名残りなく燃ゆと知りせば皮衣、思ひのほかに置きて見ましを》
(あとかたもなく燃えてしまうものと知っていたら、この皮衣、美しかっただけに、ただ鑑賞しているだけでも良かったですね)
《年を経て浪立ち寄らぬ住之江の待つかい無しと聞くはまことか》
(波が寄るはずの住之江にも波が寄らないようにこちらにおいでにならないのは、貝が無かったので私が待っていても仕方ない状態とお聞きしました。
お身体を痛められたというのは本当でしょうか:住之江に立つ波−こちらに立ち寄らない、貝無し−甲斐無しなどの掛詞が複雑に組み込まれている)
《甲斐はかくありけるものをわび果てて死ぬる命をすくひやはせぬ》
(姫様から文を頂くとは、苦労した甲斐があったというものです。しかし私はもう長くないでしょう。私はあなたに愛して欲しかった)
■文中に付けた(*)の部分の補足説明
(*1)竹取の翁の年齢について原典の竹取物語では5人の求婚者が残ってこの中の誰かと会いなさいと翁が姫を説得しようとする時「自分はもう70歳だ」と言っているのに対して、かぐや姫昇天の直前の所で「まだ50歳程なのにすっかり老け込んだよう」と書いている。5人の求婚者が残った頃を17-18歳くらいとした場合、昇天の頃は23-25歳くらいとなるので、昇天の時に50歳なら25-27歳頃に竹の中から姫を見つけたことになる。それでは「翁」と呼ばれるには若すぎること、この物語はもう子供ができないと諦めていた夫婦に子供が授かるパターンの物語にも見えることから、この偽娘物語では「自分はもう70歳」の所の年齢を採用することにし、結果翁が姫を見つけたのは52-53歳頃、昇天は76-77歳頃という計算になる。
(*2)かぐや姫の年齢について、原典の竹取物語では最初の方で、わずか3ヶ月ほどで成人の背丈になったと書いている一方で、最後の方で翁が「私たちはこの子を20年余りも育てたのに」と言う所があります。竹取物語は恐らく数人の書き手が加筆したことによりあちこち矛盾点があり、これもそのひとつと考えられます。五人の求婚者とのやりとりで最低3年は経っていることを鑑みると、むしろ普通に育って15歳で成人させたと考えた方が「20年余育てた」という翁の言葉と矛盾しないと思われます。
この偽娘物語はだいたい次のような設定で書いています。
15歳 成人式
17歳 多数の求婚者の中で5人の貴公子が残る
21歳 帝が姫に関心を持つ。強引な行幸
24歳 月からの使者が来る
なお成人式である笄年は15歳であるが、実際には律令制では女子は13歳になれば結婚可能と定められていた(現在なら小学6年生。男子は15歳以上で結婚可能)。そういう定めができる前はだいたい女子は初潮が来れば大人になったとみなされ、結婚可能と考えられていたのではとも言われる。
結婚年齢は後の時代になるほど幼くなっていき、政略結婚では5〜6歳で結婚させる場合もあり、酷い場合は生まれる前に婚約してしまうというケースもあったらしい(生まれてみたら男同士や女同士だった場合は破談)。
(*3)かぐや姫の名前について垂仁天皇の妻の迦具夜比売が元ネタとする説があります。古事記によると開化天皇と竹野比売の間の皇子が比古由牟須美と言い、その子供に大筒木垂根王という人があって、その娘が迦具夜比売といって、垂仁天皇と結婚して袁耶弁(をざべ)王という子をなしています。竹野とか筒とか、この付近は竹取物語を連想させる名前が現れています。実際「筒木」というのは筒状になっている木ということで竹の意味ではないかという指摘、またツツキというのはツツ(星)とツキ(月)がくっついた名前のようにも見え、竹から生まれて月に帰るかぐや姫との関連も想像できます。
また、大筒木垂根王の弟には讃岐垂根王という人があり、竹取の翁の名前として挙げられている讃岐造も連想させます。古事記は大筒木垂根王と讃岐垂根王にはあわせて5人の姫がいたと書いています。
(*4)当時は木綿はまだ無い(正確には生産技術が確立していないため超高価であった)。当時、布といえば高価な絹(真綿)か安価な麻の2択である。
またこの時代には傷跡を縫うという技術も確立していない。
(*5)求婚者が5人と書いているにもかかわらず、現存の竹取物語原文では3人目の求婚者の所で「いまひとり(最後のひとり)」という表現を使っている。この物語には「3月で大人くらいの背丈に成長した」とか、数人の求婚者が「3年掛けて品物を調達した」とか、かぐや姫が天皇と3年間文通したなど、3という数字が多用されており、この物語が最初に成立した段階では求婚者の数も3人だったのでは推測されている。
なお、今昔物語集巻31第33話にも「竹取翁見付女児養」というものがあり、こちらの難題も3件である。
・「空に鳴る雷」→大伴大納言の龍の珠
・「優曇華と云ふ花」→庫持皇子の金銀玉の枝
・「打たぬに鳴る鼓」→火鼠の皮衣?
なお皮衣は原文では「裘」という漢字を使っているが難しい字なので今回の物語では皮衣と書き改めた。
(*6)武雄温泉は神功皇后(恐らくAD400年頃の人)が開いたとされている。
武雄の町の背景にある御船山(猫の耳のような形をした双峰の山)は神功皇后がここに朝鮮出兵のための船を繋いだという伝説が残る。実際に昔の水系では武雄から出兵の基地となった唐津まで水路を伝って山越えに船を移動させることが可能であったようなので、恐らくはこのあたりでも船を建造したのだろう。
九州で最も有名な別府温泉はもう少し新しく、平安時代以降、主として鎌倉時代に開発された。
(*7)竹取物語の原文では天女が「わが名はうかんるり」と言っており、通説ではここは「わが名は、うかんるり」と読む。しかし「わが名、はうかんるり」であって、天女の名前は「はうかんるり」なのでは?という説もある。もし「はうかんるり」なら「宝冠瑠璃」という意味かも知れない。
この庫持皇子の冒険談はこれだけで1つの物語として成立するほどの内容がある。
日本版シンドバッドの冒険である。
(*8)この時代の天皇のセリフには本来自尊敬語を使用すべきですが、それをやると、セリフを誰が言っているかが読み取りにくくなるので、今回の物語では自尊敬語は一切使用せず、現代標準語風の相対敬語で押し通しています。
(*9)天皇の妻のランクは奈良時代頃までは大后・妃・夫人・嬪である。定員も定められており、大后(正妻)は1名・妃2名・夫人3名・嬪4名で天皇は最大10人の妻を持つことが許されていた。
女御というのは本来嬪の別称という説と、嬪が後に女御と更衣に別れたという説がある模様。また大后(おおきさき)は光明子以降は皇后と称する。
平安期以降は妃・夫人の制度が廃れてしまい、皇后のすぐ下が女御となって、女御の地位が高まり、皇后とするべき女性も最初はいったん女御として入内する風習となり女御入内の儀式が派手に盛大なもの(後の大婚相当)と化したようである。
この物語は基本的には奈良時代を想定して書いているので、当時の女御(嬪)は平安時代以降の更衣に相当する。また嬪という名称が現代の読者にはあまり馴染みがないことからここでは女御という言葉を使用した。
奈良時代の律令制においては、妃は皇女、夫人は3位以上の者の娘、嬪は5位以上の者の娘とされている。かぐや姫の入内に伴い父・讃岐造は5位を与えられたので、かぐや姫は嬪(女御)の資格を得たと考えられる。(むしろ嬪にするために父親を5位に列したと考えるべきかも)
(*10)かぐや姫の殿舎は天皇と結婚するために父親を5位にしたと考えると最低ランクということになり、これが平安時代なら桐壺が与えられていた所だろう。桐壺はそこに行くまでに多数の殿舎を通過する必要があり、帝の渡りが多いといたづらに嫉妬を引き起こす。下記は平安京の七殿五舎の配置。
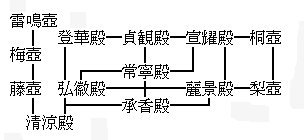
当初は後宮の中心に位置する常寧殿が皇后の居所とされたが、後に清涼殿に近い藤壺や弘徽殿が与えられるようになった。伊勢物語で有名な藤原高子は常寧殿に住んだが、藤原道長の娘で紫式部の保護者である藤原彰子は藤壺に住んでいる。彼女のライバルで清少納言の保護者である藤原定子は登華殿とされる(梅壺に居た時代もあるもよう)。藤壺に住んだ人としては陰陽師に出てくる藤原安子(藤原兼家の姉)などもいる。
平城京の後宮の建物については調べてみたものの、どうしても分からなかった。
平城京自体、あまり研究者が多くない雰囲気もある。
いちばん遠い所にある桐壺に住む身分の低い女性が帝の寵愛を最も受けているという構図は、かぐや姫が男の子を産めば、かぐや姫が桐壺更衣、その子供が光源氏になってもおかしくない構図である。かぐや姫が輝く姫なのだから、その子供も光輝く君になりそうだ。

